コンビニの歴史(解説編)
 コンビニの発祥はアメリカと言われています。1927年に、『サウスランド・アイス』という会社が、氷を売る売店に日用雑貨や食料品などを品揃えし、毎日営業を始めたのがそのルーツといわれています。
コンビニの発祥はアメリカと言われています。1927年に、『サウスランド・アイス』という会社が、氷を売る売店に日用雑貨や食料品などを品揃えし、毎日営業を始めたのがそのルーツといわれています。 このお店は、後に営業時間が朝7時から夜11時までということにちなんで、『セブンイレブン』と名づけられ、アメリカで発展していきました。つまり、コンビニの発祥は、現在の日本コンビニ界の王者、セブンイレブンということになります。
このお店は、後に営業時間が朝7時から夜11時までということにちなんで、『セブンイレブン』と名づけられ、アメリカで発展していきました。つまり、コンビニの発祥は、現在の日本コンビニ界の王者、セブンイレブンということになります。 日本で最初のコンビニについては諸説あり、コンビニの定義によりいろんな見方がされているようです。
日本で最初のコンビニについては諸説あり、コンビニの定義によりいろんな見方がされているようです。1969年ののマミーを最初とする見方、翌1970年のココストアを第1号とする見方、1973年のファミリーマートや1974年のセブンイレブンを最初とする見方などがそれです。
日本のコンビニといえば、現セブンイレブンの鈴木敏文会長。彼は元々は日本で圧倒的シェアを誇る雑誌の卸問屋『トーハン』で中間管理職をしていました。トーハンにおいても周囲が驚くような実績(新刊ニュースの発行部数を激増させたetc)を残していた鈴木氏は、31歳のときに、イトーヨーカ堂のオーナーである伊藤氏から説得され、イトーヨーカ堂に転職しました。
当時の小売業は、品数、売場面積至上主義的な面があり、品数が多い(売場が広い)=売上が多い=利益が多いという、極めて単純明快な理論が業界を支配していました。鈴木氏は、この業界の常識に疑問を呈し、必ずしも売上拡大だけが利益拡大の手段ではないことを、徹底したロス管理で示してみせ、イトーヨーカ堂の役員へと出世していきます。
彼が40歳くらいのとき、アメリカのコンビニの話を聞きつけ、周囲の猛反対を押し切って、当時アメリカでセブンイレブンを展開していたサウスランド社と契約を交わし、日本のコンビニ業界を切り拓いてきました。
各社の沿革を見ていて興味深いのは、ファミリーマート。
ここは、なんとセブンイレブンよりも1号店の出店が早かったんですね。経営陣が鈴木氏のように突っ走ることができなかったのかどうかはわかりませんが、ファミリーマートの2006年5月期の店舗数は6700店超。トップのセブンイレブンは11000店を超えています。倍とまでは言いませんがそれに近い差をつけられてしまっています。
ここで、上位各社の出店推移を比較してみます。
| 店舗数 | セブンイレブン | ローソン | ファミリーマート | サークルK | サンクス |
| 100店 | 1976(2) | 1979(4) | 1980年頃? | 1983(3) | 1983(3) |
| 1000店 | 1980(6) | ??? | 1987(14) | 1991(11) | 1993(13) |
| 2000店 | 1984(10) | 1986(11) | 1990(17) | 1997(17) | 1997(17) |
*ファミリーマートはエリアフランチャイズの店舗数をカウントしてないのかもしれません。
表を見て言えることは、やっぱりセブンの出店スピードの速さです。100店出店するのに2年、1000店でも6年、2000店だとたったの10年。競合他社と比べても、常にトップのスピードです。
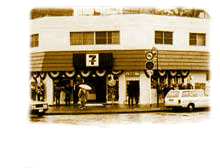 また、フランチャイズ展開を最初にスタートしたのもセブンイレブンでした。
また、フランチャイズ展開を最初にスタートしたのもセブンイレブンでした。「最初はまず直営で実験を。。。」
という悠長なことはせず、最初からFC店(酒販店からの切り替え)をオープンさせたのです。
このセブンイレブンとローソン、ファミリーマートの3社は、コンビニ業界の覇を競うべく出店競争を展開してきました。 『イトーヨーカ堂のセブン』対『ダイエーのローソン』対『西友のファミリーマート』。当時はこうした図式で見られていたのではないかと思います。
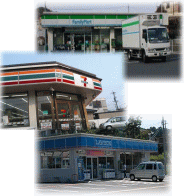 出店方式も3社3様です。
出店方式も3社3様です。”面重視”で徹底したドミナント方式を採用したセブンイレブン、ドミナントを見据えつつも”線重視”で出店エリアの拡大に重点を置いたローソン、二つのおいしいとこ取りを狙って(?)、地元有力企業の力を活用できるエリアフランチャイズ方式を採用したファミリーマート。
今になって振り返れば、セブンイレブンの圧倒的な一人勝ちであり、「エリアのつまみ喰いのローソン」とか、「他人頼りのファミマ」とか揶揄される部分もあるのかもしれませんが、それぞれがそれぞれの戦略を実行し、コンビニ業界の天下取りを目指したのは非常に面白いことです。
そして、それは今後もまだまだ続けられていくことでしょう。
ただし、コンビニの発展について懸念材料もあります。
それは、過剰競争と類似異業種の台頭です。
100円ショップ、生鮮コンビニ、スーパーの24時間営業、ドラッグストアの台頭など、コンビニの客層を取り込むような業態がどんどん台頭してきています。 現状のコンビニに取って代わるようなことにはならないと思いますが、コンビニ業界を縮小させるような事態は十分考えられます。
競争が激しくなることは消費者にとっては好ましいのですが、業界にとっては必ずしもそうは働きません。
『競争が激しい=儲からない』という図式になってくるからです。
コンビニの歴史は数多くのオーナーの歴史でもあります。 日本には4万店を越えるコンビニがあると言われていますが、そのほとんどにオーナーがいるのです。 直営店とか、複数店とかを考慮に入れても、3万人以上のオーナーがいるのではないでしょうか?
彼らが儲からなくては、コンビニの未来は明るくはなりえないと思います。
こんなことを考えると、10年後、コンビニはどうなっているのか、ちょっと不安になったりもします。
 コンビニについての情報、商品レビューサイト、コレクターズサイトなど、コンビニで扱っている商品、サービスに関係してくるサイトとの相互リンクをジャンジャンやっていきたいと思っています。ご希望の方は下の方にあるアドレスからどうぞ。
コンビニについての情報、商品レビューサイト、コレクターズサイトなど、コンビニで扱っている商品、サービスに関係してくるサイトとの相互リンクをジャンジャンやっていきたいと思っています。ご希望の方は下の方にあるアドレスからどうぞ。